みなさんこんにちは。Supportia学長の瀧澤です。
ここまでいくつかの文章を投稿してきましたが、まともに自己紹介もせずに進めてきてしまいましたので、少し長めに、私の人となりが多少でも伝えられたらと思いまとめてみることにします。
私は千葉県松戸市生まれの37歳です。小中高と千葉県内で過ごし、大学からは東京に出ることになりました。大学では史学科に在籍しておりましたが、教職課程も取れる大学だったので、中学校と高等学校の社会科・地歴・公民科の教員免許状を取得しました。そして2009年4月から東京都の教職員として公立中学校の社会科教員として勤務してきました。
2020年度末(2021年3月末日)をもって、12年間の公立中学校教員としての生活に幕を下ろしました。退職後は自分のやりたいことをじっくりと考え続けました。半年間ぐらい、ゆったりとした時間の中で、ふと2020年12月に亡くなった父のことを思い出しました。児童劇団を経営していた父は、よく「お金はほどほどにあればいい。自分がやりたいことをやれる人生は最高だ」と言っていました。
退職後の自分はどう生きるべきなのか?
自分の人生の今後を想像し続ける中で、原点に回帰するような感覚で、以下のようなことを考えるようになりました。
自分は教育に携わって生きてきた人間だし、今からビジネスのことをイチから学び直そうなんていう気にもなれない。自分の武器は教師として磨いてきた能力だ。数値には表れにくいかもしれない力だけど、きっとやれることはある。
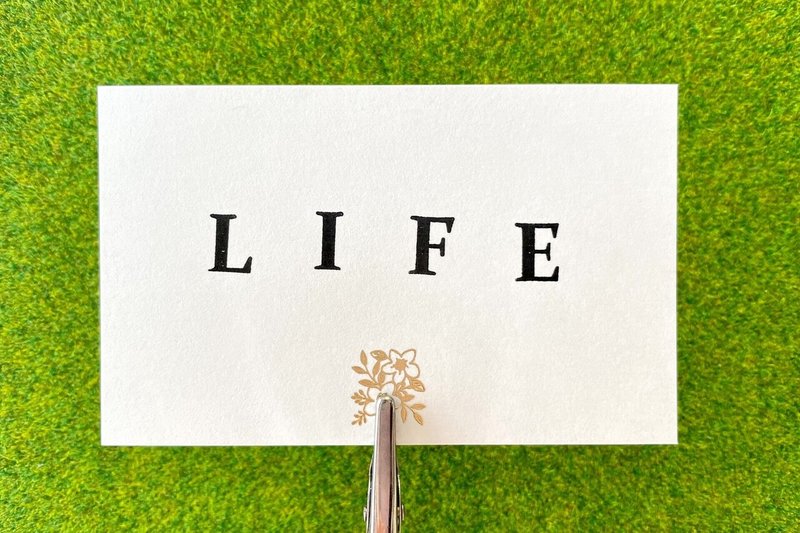
ボクシングで死にかける。死との距離感に変化。
少し話は遡りますが、私は19歳(大学1年生)の頃にボクシングの試合で事故に遭いました。急性硬膜下血種という、最悪の場合命を落とす、70%の確率で言語障害か半身麻痺が残るという大ケガです。それ以降、「死」が自分の背後すぐのところにあるものだという認識に認識に変わりました。すぐに人は死んでしまうという意識を19歳でもてたことは幸いでした。
死ぬときにはきっと自分の人生を問う場面がくると感じました。
お前の人生はどんなものだったのか。生きた意味はあったのか。誰かに貢献することはできたか。
以降、「貢献感」は自分の生きる上でのテーマとなりました。教師であった自分は、教育という分野で未来を担う子どもたちを支えることに微力ながら貢献することを目指す。いずれまた死が迫ってきたときに、自分の生が何を残したのか明確に答えられる人生にしたいと思います。

しかしその一方で、私が尊敬してやまないタモリさんは「生きることに意味などない」とおっしゃっています。考えることなんて「いい天気だなあ」「明日も晴れるかな…」ぐらいでいいんだ、と。
私もタモリさんのように軽やかに生きたいと何度も思いましたが、土台となる性質が異なることに気づき、断念しました。タモリさんを観ていると、つまらない真面目さや繊細さ、慎重さをもつ自分が嫌になることがあります。それでも自分なりの、心にフィットした生き方があるはずだと思いながら生きています。
本当は、そんな難しいようなどうでもいいような、答えが出るわけでもないことを考える暇も余裕もない人生こそが一番いいような気もしたりして。
話の舞台が大きく変わりますが、古代ローマ帝国では、戦争に勝利した後に将軍が凱旋式パレードの際、兵士たちに伝えた言葉があったそうです。
ラテン語で「Memento Mori」=「死を忘れるな」
この言葉の趣旨は「今は食べて飲んで、派手に陽気に楽しもう。明日になれば、我々は死ぬから。」といった内容だったそうです。
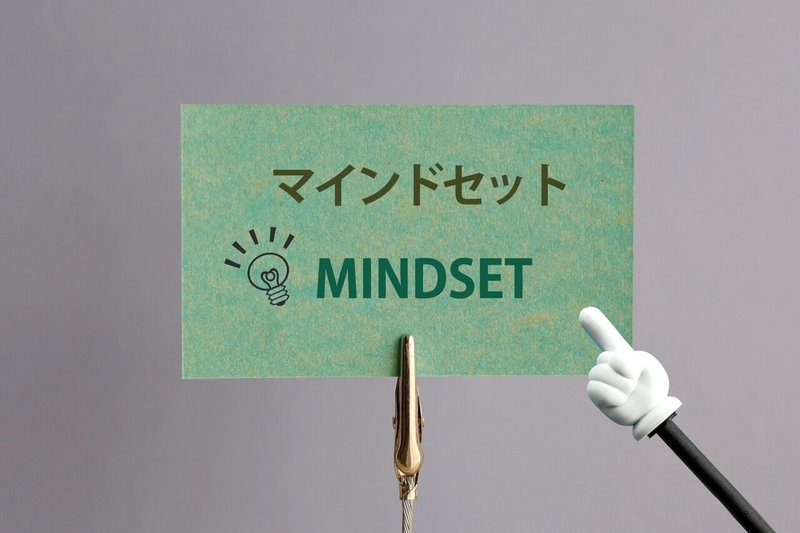
今を生きる私たちがこの言葉から何を受け取るべきかはそれぞれの価値観によりますが、私は経験上、死を意識したことからこの言葉を知った時には深く共感した記憶があります。
影があるから、より明るく見える。
闇夜があるから清々しい朝日を拝める。
表裏一体。
自分がどのように生きるかを決めるのは、他でもない自分自身です。
そして、自分自身のことは自分しかわからない。
けれど、自分自身を理解することはすごく難しい。

自分を外側から眺める力(=メタ認知)を獲得するには、自分に問い続けて自分の特性や思考のクセや傾向を理解することに努めるしかない。
その問いは、自分で生み出すのと同じくらいかそれ以上に、他者の考えに触れることによって生まれ、ひとりよがりでない自己理解につながるのではないか。
そんなことを考えて、国数英やお金・ビジネスの話だけではなく、道徳や倫理に近い内容も、授業として設定することに決めました。Supportiaへの参加が、自己理解の一助になれば幸いです。
Supportiaの自由参加型のチャット&トークという授業では、正解はないけれど、受け止め方や捉え方の違いが生まれるような内容を扱い、哲学対話のような時間を共有します。参加する大人も、大真面目に参加します。
皆さんと激論を交わせる日を楽しみにしています。
